忘れられない本
情報工学科三年 向 美紀
『そこに僕はいた』この言葉を聞いて皆は何を想像するだろう。私はなぜか、このタイトルを強く気に入っている。七文字。たった七文字の言葉だけど、私はこれからもずっと忘れないだろうと思う。
この本と出会ったのは中学生のとき。学校で習ったのをいまだに覚えている。主人公の男の子である僕と、いつの間にか遊び仲間となっていた、あーちゃんという片足が義足の障害をもった男の子。いつも一緒に遊んでいた二人。でも大人達からは、あーちゃんと一緒に遊ぶときは気をつけなさいなどと言われ、主人公の僕は複雑な思いになり苦しんでいく。しかし、自分が目を失明しかけたことにより複雑な思いがとけ何かかわってくる。そういう内容であるノンフィクションのストーリーだったのを覚えている。もちろん、この内容に相違はない。
一見、中学校の教科書に出てくるわけだなぁと思いそうになる、ありがちな本に見える。でも、なぜ私がこの本に執着し、この本の内容までをも覚えていたか? それは今、久々に読み返してみてようやくわかった気がする。
その本を読むまで、幼いときから学校では、「差別はいけない」だとか「障害者も皆同じだ」とか、物凄く抽象的で且つ「○○はこういうものだ」という理論的に組み立てられた考えを社会秩序として、耳にたこができるぐらい何度も聞かされ、教わってきた。もちろん、道徳的な学習がいけないといっているわけではなくて、私も必要だと思う。けれども、本当に今まで教わってきたことは全てが全て、当てはまるのだろうか? と、思うような内容がこの本にはつまっていた。
本の中で、あるときこんな場面があった。主人公の僕やあーちゃんを含め何人かで皆で山の急斜面に基地を作ろうとしたとき、義足である、あーちゃんだけが登れずにいた。
「すまんかった」と主人公である僕が誤り手を差し出すと、
「何で謝るとや。それになんなこの手は。」
と、あーちゃんが言って帰ってしまった――。
あーちゃんはなぜ帰ってしまったのだろうか? 初めて読んだとき私は変な違和感を覚えた。私にはなぜあーちゃんがそう言って帰ったのか不思議でたまらなかった。そのときの私には、あーちゃんが、自分が障害をもっていることを気にしないで楽しみたいのに僕は、あーちゃんにとって一番されたくない態度をとってしまっていた、変な気を使って欲しくない、普通にしたいだけなのに…だからあーちゃんは辛かったんだという気持ちをなかなか受け入れる事ができなかった。今まで気づかいだと思っていた事、それがこんなにも傷付けることだったとは…。私は本当にもやもやした気持ちでいっぱいだった。
もう一つこの本の中で一番大きくショックをうけた場面があった。主人公の僕があーちゃんと遊ぶことを苦痛と思わなくなり、ハンディを背負っている人だという意識がなくなり本当に自然に手を差し出せるようになった頃、僕があーちゃんに、
「あーちゃんは、どうしてそうなったと?」
と義足を指差して聞いた場面。するとあーちゃんは笑顔で、
「電車にはねられたとたい」と言った――。そう書かれてあった。
私は又変な違和感を覚えた。驚きを隠せなかった。「何でそんな事聞くんだ?! とても失礼ではないか」と私は思っていた。前は、そんなノンフィクションの話を受け入れることができなかった。今思えば、僕が言った言葉はごく自然な言葉なんだなぁと思える。いつの間にか身に着いていた変なマニュアルに囚われずにでた、「何で?」って思う当たり前の質問。逆にわざと聞かない方がどこかで見下しているんじゃないかなって思う。確かに唐突に聞くのもびっくりされるかもしれないけど本人同志が本当に素直な気もちであれば分りあえるんだなぁと思った。私の中でこの事がこの本を印象付ける事になった一番の理由だと思う。
私は今まで幼いときから道徳の授業や人権学習なので習ってきた事が全て間違っているとは思わない。けれど、そんなマニュアル通りに習えば習うほど、もし自分があーちゃんのような人に出会ったら変にギクシャクしてしまうような気がする。
私はこの本と出会えてよかったと思う。私の中で鎖で繋がれていた何かが開かれ一気にパァッと明るくなったような気持ちになった。
確かに差別をする事はいけない事だと思うし、皆同じだという概念は変わらない。しかし、変に気を使い過ぎではないだろうか?この子は特別なんだというレッテルをさらに確認付けているだけのように思えてくる。色んな人がいるという事を知る必要はあると思うが、変なマニュアルに囚われていた今までの自分は何だったんだろう? とこの本を読み返して本当にむなしさが込み上げてくる。
ごく当たり前の事、自然な事、普通の事が忘れられてしまった世の中、できなくなってしまった世の中。そんな世の中だからこそ、自分は何を感じ、何を学び、何をする事ができるのだろうか? 実際は学校で教わってきたマニュアル通りなんか上手くいかない。この本と出会ったように又これからもっと大きなショックを受けるような事があるかもしれない。やはり幼い時から知らぬ間に身についてきた事は別の事をうけ入れようとするのはなかなか難しいから、その代償は大きいと思う。
「あの人と関わったら何かあったら困るからやめとこう」とか「○○はこういうものだ」というふうに決め付けたくないし、変なマニュアルにも囚われたくない。それが今の本音なのは事実だし、この気持ちはこれからも変わらないと思う。でも、そんな世の中では、ないことも事実だし、実際に自分は本当にこの信念を貫きとうせるか?と聞かれると正直分からない。キレイごとばかり並べてるんじゃない!! と、逆に社会から怒られるかもしれない。でも、キレイごとって呼ぶ人もいるけど、それって大切じゃないのかなって思う。誰だって、あーちゃんのように普通に接して欲しい、皆と違うところはチャンと受けとめて欲しいと願っている。本当にだれでもそう思っているはず。
これから私が超えていく壁は物凄く大きいだろう。挫折も何度もするだろう。でも始まったばかり。これからたくさんの人と出会い、考えさせられ、マニュアル通りに行かなくて悩み、何度となく人生の岐路に立たされるだろう。そんなとき、この本と出会ったときのように、たくさんの時間がかかってもいいから、全てを受け入れ、そしてそこから自分の答えを探していきたいと思う。
『そこに僕はいた』この言葉を聞いて皆は何を想像するだろう。私はなぜか、このタイトルを強く気に入っている。七文字。たった七文字の言葉だけど、私はこれからもずっと忘れないだろうと思う。
書名 そこに僕はいた 著者名 辻 仁成 出版社名 角川書店
「アルジャーノンに花束を」を読んで
一年三組(T) 天野 未来
知的障害者のチャーリイは読み書きも十分にできず、その言動はまるで幼児のごとく、単純なことも理解できない青年だった。幼い頃からチャーリイは孤独だった。学校ではいじめられ、実の妹に嫌われ、彼が最も愛情を求めていた母親にさえ見放された。周囲の人々は、彼が障害者であることを嘲笑し、彼の無知や鈍重さを軽蔑した。チャーリイはその知能の低さゆえに自分が受けている仕打ちさえも理解できなかったが、自分と他者との間には常に、お互いをつなぐことを許さない障壁があるということには気付いていた。
チャーリイと他者との間に障壁を築いていたもの―それは「知能」であった。その欠乏はお互いの意志の疎通を妨げ、自分と相手をつなぎあわせることを許さず、チャーリイを孤独へと追いやった。ゆえにチャーリイは知能を手に入れることこそ障壁を取り払う方法であると信じていた。
しかしチャーリイが人為的に知能を増大させる手術の実験台に選ばれ、超知能を手に入れたとき、その考えは無惨に打ち砕かれた。
かつて知能の低いチャーリイを散々からかい嘲笑していた彼の職場の同僚たちは、チャーリイが教養のある天才と化すと途端に彼を避けるようになり、しまいには店長に陳情し、彼を職場から追い出した。しかし自分を嘲笑していたとはいえ、チャーリイにとって同僚たちは仲間であり、友人だったのだ。職場から追放され、友人を失い、肉親の所在も知らないチャーリイは懊悩の中をさまよい続けた。
知能を手に入れても、依然として―いや、前にもまして、チャーリイは孤独になってしまった。
なぜなら、チャーリイと、彼を嘲笑する人々との間に真に障壁を築いていたのは「知能」ではなく、ただ単に周囲の人々の「無常さ」と「エゴ」だったからだ。同僚たちを含め、チャーリイの知能の低さを嘲笑していた人々は、チャーリイの人格を軽視して理解しようともしなかった。チャーリイがどんなにひたむきに生きても、彼らにとってはただの「うすのろ」だったのだ。『弱肉強食』? 知能障害者を嘲笑するような人間が強者であるはずがない。ただ知能の低いチャーリイを弱者とみなし、歪んだ優越感の影に隠れていただけだ。このような人々がもし、相手を思いやる心をもっていたならば、チャーリイはどんなに救われたことだろう。
それは私たちにも言えることではないだろうか。私たちは一人一人が個人であり、人種、文化、経済的又は社会的身分から、年齢や性別、性格、知能レベルにいたるまで、それぞれが異なるものを持っている。そして私たちは、自分と異なるものを持つ相手との間に境界線を引きがちである。やがてそれは障壁となり、そこにはしばしば争いや憎しみや誤解が生まれてしまう。それは、いじめであったり、差別であったり、戦争であったりする。この障壁を消すことができたなら、どんなに視野が明るく開けるだろう。どんなに世界が美しく見えるだろう。それを可能にするには、もっとお互いを尊重し、理解し、認めあうことだ。相手の痛みをともに感じ、思いやらなければならない。そこにはきっと、依存も疎外も存在しない、各々の独立があり、真の信頼と愛があるはずだ。チャーリイが自分と同じく人為的に知能を増大させる手術の実験台となった、アルジャーノンというねずみの亡骸に花を供えたように。たかがねずみ。だがチャーリイは、その痛みや悲しみを知っていたから、アルジャーノンの死のために涙を流したのだ。
それは知らず知らずのうち、彼が求めていた「他者とのつながり」を実現させていた。相手に対する思いやり、共感する心、愛情。それは相手とのあらゆる障壁を消し去り、固く確かな絆を作り出していた。自分と他者との間に障壁を築くのは、性質の違いでも、力の差でもない。問題はそんなことではない。問題は、そのような自分と相手との異なる点を障壁だと決めつけてしまう自分自身にあるのだ。自分と他者にいくつか、いや数多くの異なる点があったとしても、私たちは何ら変わらない同じ生命であることを忘れてはならない。
見返りも期待せず、自分の損得に関係なく本当に相手を思いやり、尊重し、理解し、認められる、そういうひとに何人か出会ったことがある。その人たちは孤独と戸惑いの中にいた私の心に架け橋を渡し、人間と人間のつながりとは、ときに誰かを傷つけ、不快にさせ、疎ましいものになってしまうが、相手を心から思いやることによってすばらしいものになり得るものだということを教えてくれた。だから思いやる心を何よりも大切に・・・それはこの本の作者の想いである。チャーリイが本当に求めていたもの、そして彼を癒したものは、「知能」ではなかったのだから。
書名「アルジャーノンに花束を」
著者名「ダニエル・キイス」
出版社「早川書房」
クリエイター
電子工学科二年 池田健太郎
もしも、鳥のように空を自由に飛べたら。もしも、自ら乗り込んで自在に操れるロボットがあったら。もしも、自分そっくりのロボットがいて宿題をしてくれたら・・・。
小さい頃、誰でも一度はそんなことを考えたことがあるだろう。私もそんなガンダムやドラえもん、スーパーマンのような存在に憧れたひとりである。不思議な力で大空を自在に飛び回り、助けを呼ぶ声に一目散に駆けつける。人知を超えた怪力でバスでも橋でもひょいと持ち上げ、あっという間にもと通り。山のような宿題も、ポケットから出てくる不思議な道具でちょちょいのちょい。換装すれば深海だって宇宙だって地底にだって自由に行ける。
しかし、そんなことは漫画の中だけの話で現実にそんなロボットができるはずがない。誰だってそう思っていただろう。
ところが、それを夢物語で終わらせなかった人たちがいた。現在、世界中のいたるところで開発が進められ、一歩また一歩と実現に近づいている。最初はクモのような形をしていたが、今では二本の足で立って歩き、楽器まで演奏できるようになった。ロボットアニメに憧れた自分としては実に喜ばしいことである。
また、人型ロボットの開発と並行するかのように、生物の遺伝子を組み換える研究も進歩してきた。植物に対して行なわれ始めた実験も、今では動物へ、そして人へとその対象を移してきた。「害虫に強い作物を作る。」「農薬にも強い作物を作る。」そういった目的で始まったこの研究は、最近では形を変えて医療の現場で生きている。例えば今まで取り除くことが困難だったガン細胞を、その遺伝子を組み換えることによって死滅させるといったことができるようになったのである。
これらは一見すると人類の輝かしい進歩に思える。だが、よく考えてみてもらいたい。確かにロボットができたおかげで危険な場所での作業や観測なども行なえるようになったし、遺伝子治療ができるようになり多大な危険を伴う手術もしなくて済むようになった。しかし、本当にそれだけだろうか。
まず、ロボットの場合で考えてみる。私達は無意識のうちに「ロボットはプログラムされたことしかできない。だからロボットは道具である。」と思い込んでいる。だが、これからの時代にはそれは大きな間違いである。ロボットはどんどん進化している。最新のロボットはプログラムされたことだけでなく、今までのデータと複合してより適切な行動をとることが可能である。これはヒトが行動するときと同じ、あるいはヒト以上に経験を生かせているかもしれない。ただ、全く新しいことを考え出すという点においてはヒトの方が優れていると言えるだろう。しかしながら、現代人は新しいことをひらめく力が徐々に無くなってきている。このまま、ロボットとヒトの思考に差がなくなっていったら、一体どうなるのだろう。人類がロボットの道具になる日もそう遠くない。
次に、遺伝子組み換えについて考えられることを述べる。
植物に限ってのみ進められていたこの研究は、「ヒトゲノム計画」と呼ばれる人間の遺伝子を解析するプロジェクトの終了とともに飛躍的に進んだ。このプロジェクトの結果、遺伝子のどの配列が何を司っているかということが正確に分かったので、生まれる前の胎児の遺伝子を調べ先天性の病気があれば治療するといったことが可能になった。もともとあった要素を取り除くことが出来るということは、逆に新しい要素を加えることも可能だということである。極端に言えば、超能力や不老不死といった普通ではありえない能力を人工的に作り出せるのである。先日、持久力が他の個体の約二倍もあるねずみができたというニュースを新聞で見かけた。こんなことを人間に対して行うようになったら、「スパイダーマンの兵隊」のようなものが普通に作られるようになるだろう。どこかの戦争が大好きな国にはのどから手が出るほど欲しい技術である。これに加えて、クローン技術まで人に適用しようとしているのだから大変である。「世界に一つだけの花」でも歌われているように、オンリーワンだから価値があるのだ。それなのに自分で自分の価値を無くすような事をして、正に愚の骨頂である。
これまで述べてきたように、人間の技術が進歩するに連れてどんどん人間の価値が失われつつあることが、私にはとても怖い。技術の進歩はいいことだと思う。現に私自身、技術者になることを目指してこうして電波で学んでいる。しかし、その中にも人として越えてはいけない一線がある。人は神ではないし、大いなる自然の代弁者でもない。命を己の意のままに操っていい権利など誰も持っていない、いや、持ってはいけないのだと思う。その昔、ナスカやインカを始めとする数々の古代文明があった。それらの遺跡からは、それらの文明が現代に引けをとらないほど高度に発達していたことを物語る壁画や装飾品が多数見つかっている。私には、今は無きそれらの文明が、技術だけが先走ってもそれを扱う精神の発展が伴っていないと必ず滅びるという警告を、遺跡に託して私達に伝えようとしているように思える。
今後、技術の進歩だけに心を奪われて他の命を不幸にすることの無いよう、またそういう環境に陥らないよう、自分自身技術的にも精神的にもしっかり進歩していきたい。
「メトロポリス」 手塚 治虫 角川文庫
「果てしない」ものへの憧れとヒトの強さ
情報工学科五年 岸上 沙布
私は先日『果てしない物語』という本を手にとった。「果てしない」そこに惹かれない人が居るだろうか?「果てしない」ものにヒトは常々惹かれるようにできている。永遠だとか久遠、不変だとか。実際にはそんなもの、この世に存在しない。常に総てのものは移り変わってく。だからこそ惹かれるのかもしれない。ヒトは貪欲な生き物だから、つい無いものねだりをしてしまう。しかし、永遠なるものは、ずっと変わらぬものはきっとある筈だ。人の思念に、ものに込められた思いに。「瞬間は永遠だ」そういう言葉を昔、聴いたことがある。その刹那に起きたことは、それを味わった人にとってはいつまでも変わることのない思い出だ。その瞬間は確かに訪れたのだから。だが、そんな屁理屈で満足するような人間じゃあない。やはり、゛確実゛なものを求めてしまう。
この本の主人公も――もしかすると、この本の著者も、この本を手にとる読者も――その「果てしない」という言葉に惹かれたのだ。永遠を自分の目で確かめたかったのかもしれない。
物語のおしまいはいつもちょっぴり切なくて、どこか哀しい。ハッピーエンドの物語であっても、それが終わってしまう…そう思うと悲しくなる。だが、もしこの世に「果てしない」物語が存在するとすれば…?そうなれば物語を読み終える度に訪れるあの物悲しさを味わうこともなくなり、新しい物語との出会いを要することもなくなるのだ。なんと魅力的なことだろう。しかし、やはり゛始まり”のあるものには゛おしまい゛があるのだ。この本も、そうして終わっているのだから。
この本を読んで、まず感じたのは、゛満足゛。他の本同様終わってしまったのにも拘らず、何故か満足できるのだ。何故か。それは…きっと、その人と主人公のバスチアンがともに同じ体験を味わえるからだろう。バスチアンが本を手にし、手に汗握る゛本の中の冒険”を読むのと、私たち読者が一緒に行動できる。そんな物語はなかなかないだろう。バスチアンが本の世界にのめり込めば込む程、私たちも一緒にのめり込む。一緒に味わっている、その共同感がたまらない。読書は孤独なものだから、感動を共有できる人が居る、それはとても素晴らしいことなのだ。それも、同時に感動を、スリルを共有するとなると嬉しいことこの上なかったりする。
しかし、途中でバスチアンは゛読者”から゛本の中の住人゛へとなってしまう。けれど、一度思いを共有した者同士ということが残念に思う気持ちをなくしてくれる。そうなってもまた一緒に冒険をし、スリルを味わえる、共に喜びを感じれる…そう読者は思ええるのだ。
ヒトは生きていく中で様々な望みを抱く。だけど、その望みの大抵は叶わないものだ。簡単に叶うとどうだろう?きっと無気力になるだろう、何をする気にもなれずしまいには生きることすら面倒になるかもしれない。望みがなかなか叶わないから、ヒトは頑張れる。どれだけ自分の望みを叶えられるか、望みに向かって常にヒトは努力している。中には諦めたりすることもあるが、それでもいつも諦めてばかり、というわけではない。自分なりの結末が見えるまで頑張るだろう。ヒトはポジティブな生き物だと、そう思う。どんなにめげてもまた新しい望みは生まれる。そうしてまたその望みを叶えるべく頑張れる。ヒトは意外と強い生き物だ。もし、望みが全て叶ったら?それは凄いことだ。羨ましい限りである。そう思う気持ちは十二分にある。だが、それではいけない。望んだことが全て叶えられてしまったら、それが何の努力も無しで叶えられたとしたなら、どんなに味気ないことだろう。きっと最初のうちは貪欲にあれもこれもと願うだろうが、いずれは…無気力にならざるを得ないだろう。努力をすることを放棄すればその人生は輝きを失う。その人の輝きがなくなれば人しての魅力もなくなる。人の素晴らしさはその人の努力によってのみ勝ち得られるのではないだろうか。
本の中でバスチアンは一度生きる気力を失う。全てどうでもよくなってしまったのだ。そんな彼を救ったのは、アトレーユという友達だ。友達のありがたさ、素晴らしさ、それをこの本を通して感じた。それと共にこの本を読んで私は、ヒトの強さを改めて知ったような気がする。ヒトは一人では生きられない。孤独に非常に弱い。ヒトは弱い生き物だ。だが私はそうは思わない。ヒトは確かに一人一人ではとても弱くて儚いが、ヒトは強くなれる。誰かのために強くなれる。家族であったり、友達や恋人であったり、誰のためでもいい。ヒトは愛しい誰かのために、大切な誰かのために頑張ることで成長できるのだ。「大切な誰か」の数だけきっと、ヒトは強さを得られる。私はこれから人付き合いをして生きていく中でそんな自分を成長できるような、成長させてくれる大切な人を数多く作りたいと思う。そうして日々精進し成長していければ、と願う。
「果てしない物語」 ミヒャエル・エンデ作 岩波書店
「あなたがいてくれるから」を読んで
情報工学科三年 鈴木恵理
私はこの本を読み、命の大切さをつくづく感じた。命とは、それはとてもすばらしいものであるということを。
この本は。平成九年、十四歳の少年による犯行で、娘を失った母が書いた手記である。今でも毎日のように、テレビや新聞で、事件、事故、殺人などが起こり報道されている。
聞かない日はないくらいである。この本を読み、命について考えると、とても悲しい。まして殺人は、相手の自由や夢を奪ってしまう。その人が、これから先やろうとしていた事、やりたかった事、その人のこれからの幸せから切り離してしまうものだと思う。家族にとっても、ついさっきまで一緒にいた人が、一瞬のうちにもの言わぬ姿になった悲しみは、加害者を恨んでも、恨みきれないものだと思う。
しかし、この本を読み感動したことは、娘を失った母が、奪った人を殺して仕返しをしたら、娘が喜ぶどころか、母が人殺しをした事に対して悲しむという事に気付き、自分の気持ちと戦い、みんながゆがんだ心を直していこうとしたところである。自分で自分と戦って、残酷な心と戦い、これをやっつける人間は成長していくのだとわかった。だから私も、自分と戦い、ささいな事では負けないようにしようと思う。
自殺についても同じである。誰でも「自分は何のために生きているのだろう」と思うことがあると思う。でもそこから、生きるという事はどんな事か、人間は何のためにこの世に生まれてきたのか考えてもらいたい。私もこの本を読むまでは、そのような事を考えた事はなかったが、親の子に対する愛情の深さを知り、親への感謝の気持ちは忘れてはいけないと思うようになった。
また、嫌な事から逃げるのではなく、死にたくなるほど苦しい思いをした時が、人間が本当に幸福になっていくチャンスであり、自分の人生を大きく変えていく時なのだと感じた。この世に必要ない人間なんて一人もいないと思うし、価値のない人間も一人もいないはずである。自分には価値がないように思える時であっても、決めつけないで、自分で価値のある自分を作っていけばいいのだと思う。とはいえ、自分が困難な事を克服できるかという自信はないが、精神的にお強い人間になっていきたいと思っている。
また、このような悲しい事件の犯人が、私の弟と同じ、十四歳の男子中学生だということにはショックを受けた。しかも、自分の勝手で身の知らない、ただ通りかかっただけの小学生の女の子を殺すなんて考えられない事である。その女の子の運命だと言ったらそれまでだが、あまりにやりきれない思いがする。まして、自分より弱い者をいじめるなどというのは、最低である。でも、その加害者の男の子にも親がいて、また兄弟がいるかもしれない。加害者だけでなく、加害者の親も、どれだけ悲しみ悔やんでいるか、はかり知れないと思う。
最近では、小学生による殺人も、新聞やテレビで耳にする。考えられないことだが、現実に起こっているのだ。もっと、知ってもらいたいと願わずにはいられない。
私はこの本に出会えて本当によかったと思う。大きな感動をもらい、そして命について学ばせてもらった。この気持ちを忘れずに、これからの人生、何事にもくじけず前向きに頑張っていきたいと思う。 そして、「生と死」について、痛ましい事件を、単なる悲劇に終わらせずに、一人でも多くの人に自分自身の「生と死」への探求の糸口へと変えてもらいたい。人間はすばらしい命の底力を持っているのだから。
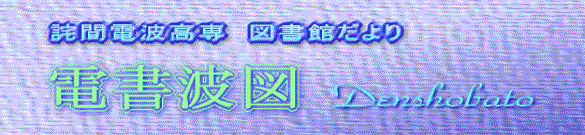

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
