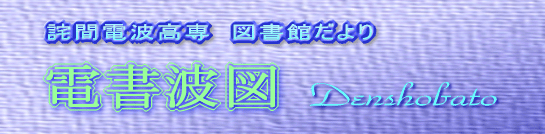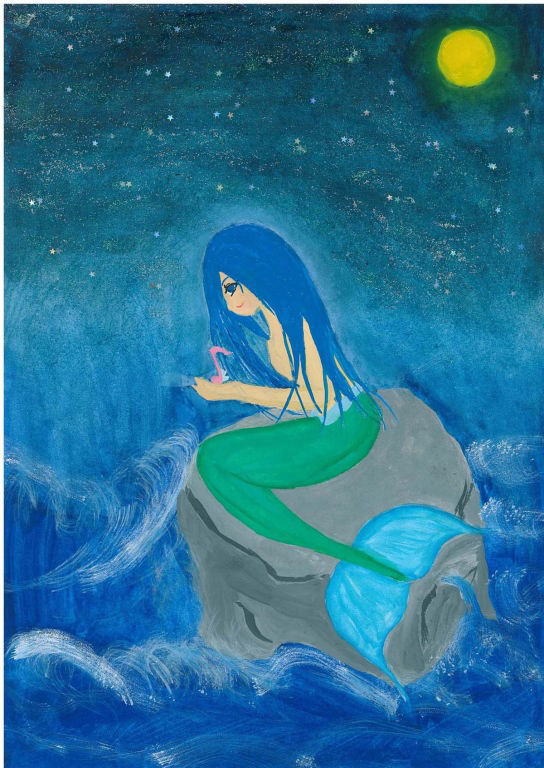|
|
|
電子工学科二年 村上 朋美 |
|
目 次 |
|
第19回読書感想文コンクール入賞作品 |
|
第一位 「本当の自分」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・情報通信工学科二年 天野 未来 |
|
第二位 「生まれてきてよかった」 ・・・・・・・・・・・・・一 年 四 組 東 愛実 |
|
第二位 不屈の精神と直向きなココロ ・・・・・・・・・・・・専 攻 科 一 年 岸上 沙布 |
|
第三位 「原爆を投下するまで日本を降伏させるな」を読んで・・一 年 三 組 斎藤 広睦 |
|
第三位 「天国の本屋」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・情報工学科三年 井下 智加 |
|
|
|
情報通信工学科二年 天野 未来 いつからだろう。自分の心にブレーキをかけ始めたのは。幼い頃は、楽しければ大きな口を開けて笑い、悲しければ大声を上げて泣き、悔しければ、ジダンダを踏んで全身でその感情を表現したものだった。成長するにつれ、少しずつ自分の感情をコントロールし、抑える術を身につけていった。それは社会という世の中とうまく付き合っていく処方であり、大人になるということなのだろうか。 私はもう随分長い間、「自分らしい生き方」をしていないと感じながら、日々を過ごしてきたように思う。他人の目を気にし、他人と同じであることを「善」とし、仮面を被りながら「本当の自分」をさらけ出すことを拒み続けきた。たくさんの友人に囲まれ、「悩みなんてないでしょう」と言われながら、明るい人を演じ続けてきた。そしてその反面、心のどこかで無理をしている自分にも気付いていた。私はもがいていた。「本当の自分」を直視する勇気と、見失う恐怖の間で・・・。 そんな時、私はドナと出会った。彼女は自閉症患者だった。「自閉症」―この病気について正しく理解している人が、どれだけいるだろう。少なくとも私は誤解していた。環境や性格など、後天的要素による精神的病いだとばかり思っていた。だが実際は、脳の先天的機能障害による病いだった。その病症については、「身体と精神は健康であるのに、精神を司るメカニズムだけがどこかうまく働かなくなって、自分を表現することはできない」と、ドナは自ら説明している。こうした自閉症の特徴を彼女も確かに示していたが、ことばを理解する能力と深い洞察力において、ずば抜けていた。そして何より、置かれた環境の中で精一杯自分の運命を切り拓いていこうとする不屈の意志が、彼女にはあった。 彼女は闘っていた。どのページの彼女も「本当の自分」を求め、懸命に戦っていた。物心ついた頃から、周りの人から「ばか」「異常」と嘲られ、周囲の世界とも自分自身とも折り合いをつけることができず、自分の殻に閉じこもり、傷つき悩み続けただろう。彼女は、「世の中」と呼ばれる「外の世界」から自分を守るため、そして逆に、なんとかその「世の中」という世界に加わろうと必死に闘っていた。 ドナは自分を守るために、社交的でにこやかなキャロルと、理屈屋でむっつりとしたウィリーという二人の人物を心の中に創り上げ、状況に応じて使い分けてきた。彼女にとって、ただ一つの「外の世界」とのコミュニケーション手段であり、生き抜いていくための手段でもあった。だがそれは、複雑な現代社会の中で仮面を被りもがいている私と、何ら変わりはないように思えた。むしろ前向きな生き方において、ドナのほうが真摯だと言えるかもしれない。苦しみながらも自分の生き方を探り続けている彼女の姿に、私は深く共感し、彼女を特別な世界の人間だとは、とても思えなかった。 また、ドナは行動的だった。どんな困難にも自分なりの解決策を見出し、決して諦めず、自分をごまかさず、自分に正直に生きていた。その生き方が、精神科医メアリーとの出会いを導いた。メアリーはドナを患者としてでなく一人の人間として受け入れ、彼女の中の「一生懸命外に出たがっている怯えた小さな女の子」に気付づいた唯一の女性だった。この出会いが、彼女の生き方をより積極的に変えた。休学していた高校に復学し、大学へ進み、さらに自分と同じ自閉症に苦しむ子ども達のために教育学を学ぶまでに成長した。それは私にとって驚異だった。彼女を突き動かす力は、どこから生まれてくるのだろう。自閉症のドナの方が私よりずっと豊かにいきいきと今を生きていた。 自閉症であることをはじめ、家族、学校、友達との葛藤など数々の試練を乗り越え「本当の自分」を見出すまでのドナの過酷な心の軌跡をたどることで、私は自分を見つめなおすことができたように思う。弱く脆い私がいた。ドナは「本当の自分」を捜し求め、私は求めながらも避ける生き方を選んできた。だが、「自分らしい生き方」を願うなら、そんな自分を打ち破らなければならないと知った。今の私には、仮面を脱ぎ捨て生きていくだけの強さや潔さはまだないけれど、「本当の自分」と向き合い、対話する勇気は、確かにドナから与えてもらった気がする。自分の中に存在する「本当の自分」を意識しながら生きていく限り、大切なものを見失うことはないだろう。人が人である以上、その心は意味を求める。悩むことは悪いことではないと気づいた。自分の生き方を真剣に見つめている証なのだと。 ドナの「世の中」に対する長い長い闘いが終わり、彼女が本当の自分自身でいられる自由な開放感に浸った時、私もまた、心に重くのしかかっていたものが、徐々に取り除かれ癒されていく自分を感じていた。 書名 自閉症だった私へ 著者名 ドナ・ウィリアムズ 出版社 新潮社 |
|
一年四組 東 愛 実 「生きる」とはなにか?なぜ生まれてきたのか?なんのために今私は生きているのか?そんな悩みを私はずっと抱えて生きてきました。人間を含め、生きているものには避けることのできない「死」というものがあります。「死」とは何かも分からない私にとっては、「生」や「死」はあまりに漠然としていて、掴み所のない存在です。最も身近ともいえる存在が、私にとっては、最も遠くかけ離れた存在のように思えてしまっていました。しかしこの本を読み、自分がどれだけ「自分自身の力で歩く」ということを放棄していたか、それに気づくことができました。 あすかの親友であるめぐみは、重度の障害を持って生まれてきました。体はほとんど動かすことができず、そして十二歳でこの世を去っていきました。私は正直にいうと、そんな人生に意味なんてあるのかと、そう思ってしまいました。しかし何度か読み返し、考えていくうちにあるひとつのことに気が付きました。この本の中で、めぐみの表情・感情を書き表しているところがあります。それはすべて「うれしそうに」や「楽しそうに」「幸せそうに」というように、めぐみは幸せな人生を送ったと読み取れるのです。そして亡くなったその瞬間でさえ、幸せそうに微笑んでいました。なぜそんなに幸せだったのでしょう?それは生きていることが生きる意味だったからではないでしょうか?私は今まで生きている意味を考え、納得のいく答えが出せず、生きていく意味などないのだと思い続けてきました。そのため自分の人生なのに人まかせで生きてきました。しかしめぐみは人まかせに生きようとしませんでした。たくさんの人に支えられ、助けられながらも、自分自身の力で生きていきました。だから生きていることに意味を感じられたのだと思います。自分は今生きているのだという自覚があったからこそ幸せだったのだと思います。めぐみの力は他人を押しのけて自分が一番になろうとするようなものではなく、ただただひたむきに自分自身の足で人生を歩んでいく力です。きっとその強くやさしい力が周囲の人の心を暖かくさせることができたのだと思います。 生きていくことはすごいこと。今生きていることがそれだけで自分の生きる意味。私はこれから後百年あるかもしれない、五十年かもしれない、もしかしたら明日には終わってしまうかもしれないこの私の人生を、せめて「生きる意味」を気づけた今からは、自分自身の足で一歩一歩しっかりと歩みだしていきたいです。そして私が私としてこの世の中に生まれてきたことを誇りに持てるような、そんな人生を歩みたいです。 ハッピーバースデー 青木和雄 吉富多美 金の星社 |
|
不屈の精神と直向きなココロ 専攻科一年 岸上 沙布 この夏、私はレモニー・スニケットの「世にも不幸なできごと」シリーズを手にした。人間は悲しい事に、他人の不幸に敏感である――良い意味ではなく、悪い意味で。自分より不幸な人間を知る事で安心したり、優越感を得たり、自分はあの人よりは恵まれていると思い込んだりするのだ。 レモニー・スニケットの書く三姉弟妹はことある毎に、行く先々で不幸なできごとに見舞われる。けれど、この本は三姉弟妹を応援したくなる。けっして優越を覚えることはない。三姉弟妹にハードルを乗り越えて欲しい、そう心から望んでしまうのだ。そして読み終えた後、それはけして幸せな終わり方ではないけれど、不思議な事に応援していた読者がいつの間にか応援されているのだ。自分も頑張らなくては、弱気になっていてはいけない、そう前向きになれる本である。 人間、生きていると幸せなことばかりではない。時には壁にぶつかり、時には挫折し、時には一人で闘わなければならない。幸せなことより不幸なできごとの方が強く印象に残るのはその時その時を必死で乗り越えようと頑張ってきたからだろう。幸せはただ感受すれば良い。しかし、不幸は自分自身で乗り越えなければならない。 レモニー・スニケットは文中で何度もこう述べている――もしもこの本を手にとったばかりなら、下におろすのはいまからでも遅くはない、ハッピーエンドの話を好むなら別の本を探しなさい――と。その言葉通りに読むことを放棄しても構わない。読む読まないは読者が決めることだから。しかし、思いきって――たとえハッピーエンドが好きであっても――読んでみると、何かしら得られるものがあるだろう。 もし自分の身に不幸が舞い降りたなら、きっと嘆くだろう。どうして自分が?そう思うかもしれない。けれど不幸は避けることのできない現実である。この本を読んで私は、ボードレール家の三姉弟妹のようにありたいと思った。不幸を悲しむ前に自分の力で打開しよう、いつでも前向きに、決して諦めずに…。そういう直向きな姿勢でいたいと思う。人生不幸ばかりではない。幸せなことは忘れてしまいがちになっているだけなのだ。不幸を嘆くのではなく、不幸を乗り越えようとする姿勢が大切なのだ。一つ不幸を乗り越えたなら、それは自分の力となる、自信となる。このシリーズを読み、私は不屈の精神、直向きな心の素晴らしさを学んだ。決して諦めなければ何らかの解決策が生まれるだろう、つまずいたり落ち込んでも、それに立ち向かう気持ちを忘れなければ、いつかきっと重厚な壁であれ高いハードルであれ乗り越えることができるだろう。 これから先、悩んだり迷ったりすることがあるだろう。そういう時こそ直向きに、そして諦めずに立ち向かっていきたい、私はそう思う。不幸なできごとは過ぎ去ればいつかいい思い出に、自分の力となるだろう。挫折して不幸がトラウマになってしまう前にもう一度だけ試してみる…その一途な心こそが前へと進む一歩なのだ。 Never give up! 世にも不幸なできごとシリーズ 最悪のはじまり 爬虫類の部屋にきた 大きな窓に気をつけろ 残酷な材木工場 おしおきの寄宿学校 レモニー・スニケット作 草思社 |
|
一年三組 斎藤 広睦 今年は戦後六十年の節目の年である。六十年前の八月,日本は広島と長崎に原爆を受けた。原爆投下によって,二つの都市で数十万人の命が犠牲になった。本当に原爆を投下する必要があったのか。原爆投下を回避する手段がなかったのか。原爆を投下した真意は何だったのか。それらについて,改めて知る必要があると思い,この本を手にした。 戦争末期,第三十三代アメリカ大統領ハリー・トルーマンとジェームズ・バーンズ国務長官は,対日政策の担当官や陸海軍の幹部らの意見を押し切り,原爆投下を指示した。その理由は,ソ連に原爆の威力を見せ付けるためや,人々から「小物」と見られていたトルーマンが自分を強く見せるためであったようである。それは則ち,政治的都合,自分の威信のためという余りにつまらない理由で,最悪の惨状をもたらし,数十万もの市民の生命を奪い,助かった人々の心身に今なお残る苦痛を与えた,ということである。そして,トルーマンらは,その生涯を終えるまで嘘の弁明を続けたのである。 本の中で著者は,歴史の世界ではタブーとされる「もしも,こうだったら……」,「もしも,そうでなかったら……」に敢えて触れ,歴史の分岐点を解説している。それらの記述から,アメリカの誤った方向へと進んでいく様子が手に取るように分かり,非常に残念に思わされた。 最近のアンケート調査によると,原爆投下が百万人のアメリカ兵を救ったとするいわゆる「百万人伝説」を信じ,広島・長崎への原爆投下を肯定しているアメリカ人が半数近くに上ったというのである。この伝説は,何の根拠にも基づかない原爆投下を正当化するために流布された虚構である。この問題に限らず,誤った歴史認識を改め,真実を知り,伝えていくことが国際社会の中で大切なのではないだろうか。 戦後,核兵器は実戦で使われることなく,冷戦終結を迎え,日本は「最初で最後の被爆国」であり続けている。しかし,核拡散が深刻な国際問題となっている近年,「第二の被爆国」が生まれないとも限らない。確かに,核による抑止力は魅力的に映るかもしれない。近隣国の核武装を危機と感じるかもしれない。だが,核武装をしたところで平和になったと言えるのだろうか。核軍縮なくして,真の平和が訪れたと言えるのだろうか。核拡散を防ぐためには,各国が一致結束することが必要不可欠である。日本は唯一の被爆国として,諸外国にも増して,核の不拡散を訴えていく必要がある。 戦後六十年。戦争を知る世代は高齢になりつつある。しかしながら,我々の世代は戦争を知ることに余りに消極的だと思う。我々は,戦争の悲惨さ,原爆の凄惨さ,生命の尊さを知り,伝えていかなければならない。そして,過去の過ちを繰り返さないよう訴えていかなければならない。 原爆を投下するまで日本を降伏させるな ~トルーマンとバーンズの陰謀~ 鳥居 民 草思社 |
|
情報工学科三年 井下 智加 私は将来何をしたいのか。どのような仕事に就き、どのようなことを考え、どのように生きたいのか。ここ最近、見えなくなってきた。考えれば考えるほど、曖昧になっていく。最後には「どうしてこの学校にいるんだろう」という問いかけが残る。 「天国の本屋」は、生きがいがない「さとし」の物語。ある日、不思議なおじさんに誘われ、天国の本屋でアルバイトをすることとなる。この店の売り物である朗読サービスを担当し、自分に合う仕事は「本屋で働くこと」だと知る。 なぜ私がこの学校にいるのか。小学校のときからパソコンをさわることが好きだった。中学校二年のとき親がパソコンを買ってきてから、ほとんど毎日のように使っていた。中三の時にはホームページを作って、自分で書いた小説を載せたりした。そういう中で「ウェブデザイナー」になりたいという夢が生まれた。高校卒業後は就職するとしか考えていなかったこともあり、この学校を受験した。夢や目標がはっきりしていたあの時。毎日がとても充実していると思えた。 「なんかオレ、すごく生きてるって感じがする。」天国の本屋で 働きながら、ある日さとしはそう思った。皆に朗読を求められる-誰かに何かを求められることが嬉しかった。しかし、そんな朗読を聞こうとしない人がいた。本屋のレジ店員である「ユイ」。そんなユイにさとしは恋心を抱く。ユイは心に深い傷を負い、心を閉ざしていた。その傷が癒えた時、彼女は現世に戻される。天国での記憶を全て消去して。叶わない恋だと知ったさとしはユイの心が癒える様、自分に出来ることをしようと決める。 誰かに求められるさとしが、誰かのために行動しようとする。生きがいを見つけて、前向きに物事を考えることが出来るようになったからだろう。大切な人を見つけられたからだろう。大切な人がいると積極的になれるかどうかわからないが、何気なく過ごしてきた毎日を大切にしたいと思えるようになるのではないだろうか。一緒にいることができる時間が限られているのなら尚更・・・。 今までの学校生活の中でクラス替えほど憂鬱なものはなかった。クラス替えの度、今まで一緒だった友達と離れる。自分から話しかけることをしなかった私は、すぐに友達を作ることができなかった。そんな毎日は重々しかった。楽しくもなんともなかった。けれど、ゆっくりではあるが、友達ができて、休み時間の度に外で遊んだりするようになった時、毎日が楽しかった。「大切な人が出来ると、大切にできる時間が増える」ということを知った。 「きっと、君を見つけてみせる」ユイが現世に帰る日、消え行く後ろ姿に言ったさとしの言葉。はっきりと私の頭にもこだました。そしてその言葉の通り、さとしはユイを見つけることができた。辿り着くまでに長い時間がかかったけれど。 どのように行動し、継続していくのか。それが夢や願いを叶えるための、一番近い方法なのだと思った。 私は将来何をしたいのか。どのように生きていきたいのか。全然見つからないけれど、この本を読む前と読んだ後の私は、何かが変わっているのだろう。 |
|
|
|
今回の読書感想文コンクールには1年生140編、2年生5編、3年生9編、4年生2編、専攻科生1編、合わせて157編の応募があり、昨年度の116編を上回りました。 |