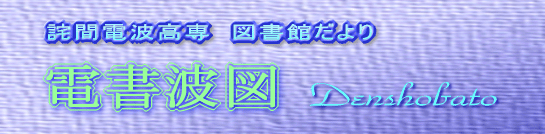|
|
|
情報工学科5年 森 啓行 |
|
目 次 |
|
第20回読書感想文コンクール入賞作品 |
|
第一位 「砂の女」を読んで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・情報通信工学科3年 天野 未来 |
|
第二位 人とのかかわり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・情報通信工学科2年 東 愛美 |
|
第二位 星の王子さま ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・情報通信工学科3年 濵野 暁子 |
|
第三位 ただひたすら想いあうこと
・・・・・・・・・・・・・・・・情報通信工学科2年 高橋 万奈 |
|
第三位 盲導犬とパートナーの笑顔 ・・・・・・・・・・・・・・・・専攻科2年 岸上 沙布 |
|
|
|
情報通信工学科3年 天野 未来 わざと心の奥にしまい込んで、他人にはおろか自分にさえも隠し通してきたもの、黒くてどろどろとしたそれを心の底から引き出され目の前に突き付けられたような感じがした。 ひとりの妻子を持ちの教師が砂丘へ昆虫採集に行き、今にも砂丘に埋もれそうな部落に足を踏み入れてしまう。そこでは、砂から村を守るためにいくつかの家が砂かきをしなければならない。一夜の宿を借りるつもりだったその男は、だまされてそれらの家のひとつに「働き手」として無理やり閉じこめられる。夜になると男は、家が潰され部落が砂に埋もれないように、その家の女と二人で砂かきをする。夜いくら砂をかいても、翌朝になればまたどっさりと砂は積もっている。男にとっては全く意味のない不毛な労働が続けられた。男は最初激しく抵抗し、幾度も脱走を試みる。しかし、しだいにその無意味な砂かきを、自分の日課として当然のように受け入れていくのである。男の心理が微妙に変化していくのである。 私はここである恐怖の念を抱いた。なぜなら、男の心理が変化していくにつれて、私の心の奥にその変化はそれほど不思議に思わない「もう一人の自分」の姿に気づいたからである。強引なまでの文章の力で、いつに間にか私も砂の世界に引き込まれていた。そして、いつしか「もう一人の自分」は男と同じように、ある心地良ささえ感じていたのだ。恐ろしい。こんなことあるはずがない。何ら文化的営みもなく、その砂穴から外に出ることも許されない生活、ただただ砂をかき、あとは食べて寝るだけの、そんな非人間的な状態に置かれた時、人はこうもたやすく変わってしまうのか。それまで男が持っていた生活や常識はどこへ行ってしまったのか。本来人間とは精神的・文化的に満たされた温かい家庭の中でこそ生きていくことができるのだ。崇高な理想を抱き、社会の中で自分の存在価値を認められることに喜びを見出しながら生きていくべきものなのだ。それらが自分の手になかったら、一生懸命追い求めなければならないし、その中でこそ「生きている」と実感できる存在でなければならない。そういう姿こそ人間の最も美しい姿なのだ。男の心理の変化は、そのように信じて疑わなかった私の心に、決定的な不安と不信を植えつけた。そこで私は「もう一人の自分」に言いきかせようとした。「これはフィクションである。なるほど、もしかしたら他人はこの男のようになってしまうかもしれないが、私は違うぞ」と。 そうはいっても、心の底でゆっくりと首をもたげてくる疑問と不安は抑えようがなかった。男の砂穴での生活、それは私たちの現代の生活にそのまま当てはまるのではないだろうか。毎日決まった時間に起き、決まった時間に通勤・通学し、決まった時間に帰宅する。自由なはずの休日でさえ、型にはまった過ごし方しかない。まるで閉ざされた世界で生活しているようだ。多くの情報が一方的に流され、それをどう受けとめるかという解説さえついてくる。私達はそれを決められたように受けとめ、皆と同じ意見と感情を持つようになる。男は言う、自由な外の世界に戻りたいと。しかし本当にこの世界は自由なのだろうか。さらに、砂穴での生活に慣れたころ、男はここの生活も外の生活と何の変わりがあるだろうかという考えに立ちいたる。不当なことを不当と思わなくなったとき、それは正当なこととして成立してしまう。私達は自由だと思いながらも、本当はその幻想の中で躍らされているだけではないのか。ただその生活の不自然さに気づかないのだ。いや、気づかないふりをしているだけなのかもしれない。 結局私もあの男のように砂の世界に閉じ込められていくのだろうか。また、男の立場に置かれた時、言い換えれば今この画一化された社会において、私は自分の理念を堅持し、自信を持って生きてゆくことができるのだろうか。ますます自信がなくなっていく。人間とは何と脆く摑み所のない存在なのか。結局、私は自分のことさえ理解していないのだ。なんと愚かしいのだろう。これまで、男の生き方を認め受け入れた「もう一人の自分」がいると述べてきた。しかし、これは逃避的な言い方であったと今は思う。真実は真実として、弱さは弱さとして、認識しなければならなかったのだ。だれもが心の底に、きれいごとではすまされない、暗いどろどろした感情をもつ。その事実は認めたくないことだけれどもそれらは確かに自分自身であるし、それなくしては一個の人間として完全にならないのではないだろうか。 私は今、それらのマイナス面に自分の一部としてむしろ積極的に目を向け、正しく認識や自覚をした上で、自分なりの生き方や幸せ、理想といったものをもう一度じっくりと考えていきたいと思う。また、そうした方向の中でそれを実現させる幅広い意味での「人間の強さ」を身につけることができるのだ。 書名『砂の女』 著者名 安部公房 出版社 新潮社 |
|
情報通信工学科2年 東 愛実 六月のテストが終わったその日に、坂道のカーブでバイクは転倒しました。バイクは壊れ、私は一ヵ月半の松葉杖生活になりました。痛みもあり、ほとんど動かずに暇をもてあましていたときに出会ったのが「五体不満足」でした。 この本の著者、乙武洋匡さんは生まれつき手足がありませんでした。しかし後ろ向きになることなどなく、いつでも前向きに生活してきたそうです。なぜそんなにも前向きに、明るく生きることができたのか・・・それは乙武さんの両親のおかげだと感じました。私は松葉杖で生活していたときは、何をするにも不自由で本当に落ちこんでいました。しかし両親はもちろん、兄弟、友人にさまざまなことを助けてもらい、私は不便ながらも学校を休むことなく通うことができました。乙武さんも乙武さん自身の明るさと、周りの人・・・特に両親のやさしさと愛情が前向きに生きるための力に変わったのだと思います。 夏休みの間に私は小学校一年生から三年生までの子供を預かるセンターでアルバイトをしていました。両親が共働きの子や片親の子たちが、平日の放課後や長期休暇に来る所なのですが、中にはあまり愛情を受けていないように思える子供もいました。そしてそんな子は、何かしらの問題も抱えていました。毎日のようにおしっこをもらす。友達とうまく遊べない。小さなことですぐに泣く。等です。大したことではないと思われるかもしれませんが、一緒に生活しているとだんだんとこの問題は「愛情不足」からきていると切実に思えてきたのです。小さな問題でも一緒に生活する人、ましてや育てる人にとっては多大な負担になると思います。そのせいで余計に愛せなくなってしまうこともあると思います。しかし乙武さんの家族を見てください。生まれたときから手足が無くても、そんなことをどうでもいいことのように思わせる明るさと愛があります。手足が無いことはただの特徴だと、乙武さん本人に思わせることのできるような愛情が何よりも大切なのだと思います。 「このふたりのもとに生を受けたことを、心から感謝したい。そして、今まで育ててくれて、本当にありがとう。」 五体不満足の中にある一節です。将来子供に心から「ありがとう」といわれたいです。そしていわれても恥ずかしくないようにたくさんの愛情をそそぎたいです。そして16年間、愛情をそそいでくれた両親に言いたいです。たくさん迷惑かけてごめんなさい。産んでくれて、育ててくれてありがとう。大好きです。 五体不満足 乙武洋匡 講談社 |
|
情報通信工学科3年 濱野 暁子 『ものは心で見る。肝心なことは目では見えない。』 とても魅力的で深く、それでいて上手く捕らえる事が出来ない不思議な魔力を持った言葉だと感じた。同時にこの言葉の持つ意味を捕らえたいと思った。だから私は、この物語の語り手である「ぼく」になって順に考えてみようと思う。 大人の不聡明さにうんざりして画家になる道を断ったのは「ぼく」が6歳の時だ。そんな彼等のおかげで本当のことを話せる相手に出会わないままずっと一人で生きてきた。6年前のあの日まで。その時、飛行機の故障で「ぼく」は砂漠の真ん中で一人ぼっちだった。そして誰もいないはずの砂漠の真ん中で奇跡は起こった。「ぼく」の一生の友達、王子さまに出会ったのだ。彼は宇宙からやって来たらしい。しかも「羊の絵を描いて」なんて突拍子もない事を言った。大人達のせいで「ぼく」は絵の勉強をしていなかったから、王子さまの納得する羊を描けないし、精神も極限に達して忍耐も限界だ。だから少し意地悪をしようと思ってざっと箱の絵を描いた。「きみの羊はこの中にいるよ」と言うと彼は「こんな羊が欲しかった」と大喜びだった。 これが、ものを心で見る第一歩だ。箱だと思えばそれはただの箱でしかない。しかし、羊がその箱の中に居ると思えば見えなくても羊は確かに存在している。ちょっと考えて紙を透かして見ようとする。しかしそれは、心で見ていないから羊は見えない。考えるのではない、心で見るのだ。 ところで大人は数を数えるのが好きらしい。大人は数で支配したつもりになる。王子さまの星にも<小惑星B612>という名前がついている。なぜだろう?「あの星は他の星と違った色をしているね」とか、「あの星は小さいね」とは言わず「あの惑星は<小惑星B612>だ」と言うのだ。それは、王子さまの星を見ているようで見ていないからだと思う。例えば友人の家にピアノがあるとしよう。「このピアノはどんな音色がするの?」と尋ねるだろうか、または、「このピアノはいくらで買ったの?」と尋ねるだろうか。きっと今の私は後者の質問をするだろう。値段でそのピアノの何が分かるだろうか。ピアノが主張したいのは音の方だ。そんな簡単な事を忘れてしまっている。ピアノのことなんて全然見ていない。年齢的にはまだ子供の私でも考え方が大人に近づいている証拠だろうか。だとすれば少し淋しい。 さて、再び「ぼく」の視点に戻る。 どうやら王子さまは、星に咲いた1輪のバラとのいざこざから星を飛び出して来たらしい。可愛がってやればやるほど横暴になる花に嫌気が差してしまったのだ。でも、花にとっても彼にとっても互いが必要な存在だった。後ろ髪を引かれる思いで彼の旅路は進む。そして地球に辿り着いた。彼はここで咲き乱れるバラと出会って星の1輪のバラの事を思い出して泣いてしまった。そんな時キツネに会って彼の考え方が変わる。自分達は絆で結ばれていると思えるようになる。キツネもバラも世界でたった1匹であり1本の存在であると気付いた。 絆は目に見えないものだ。キツネは王子さまの足音を聞いてワクワクするだろう。小麦の畑を見て金色をした王子さまの髪を思い出し嬉しくなるだろう。絆は日々を鮮やかに彩ってくれる。友達といる時は勿論、そうでない時でさえも幸せを運んでくれる。大切なのは友達と過ごした時間だ。大人のように何時間何分何秒と数えるのではなく、友達に喜んでもらえたとか、こんなことをして楽しかったとかそんな些細なことが絆になって幸せにつながっていくと思う。これも目で見ず心で見るものだ。 そろそろあの言葉の意味が分かりそうだが、ついに王子さまとのお別れだ。 「ぼく」はやっと飛行機を直せた。嬉しかったけど王子さまとのお別れの時が近づいていたから辛い気持ちで胸は一杯だった。王子さまも自分の星に帰るのだ。夜空に浮かぶ幾千もの星たちの一つで彼は一本のバラと笑っている。そう思うと「ぼく」にとって星の輝きは特別な意味を持ちはじめる。彼も自分の星で空を仰げば「ぼく」を隠している地球があると思える。 『ものは心で見る。肝心なことは目では見えない。』 王子さまの肌は白くて金色の髪をしている。それらは、体の特徴でしかない。体は命の源の器でしかないから。その器の奥に隠されているものを探そうとする時、心を必要とするのだ。「ぼく」も王子さまも互いの星を探す時、心で探しては絆に触れて嬉しい気持ちで満たされるだろう。 世界中の人々がものを心で見るようになれば、思いやる気持ちが芽生えるだろう。そうすれば、戦争をしなくなるだろう。 世界中の人々がものを心で見るようになれば、動物の悲しみが聞こえるだろう。そうすれば種の絶滅も抑えられるだろう。 世界中の人々がものを心で見るようになれば、木々の木霊が見えるだろう。そうすれば、自然に触れたくなり、大切に扱うだろう。 しかし、こんなにグローバルに考えなくても、心で見れば何かひとつ、愛おしく思えるものが見つかるはずだ。見つかった瞬間、自分の人生も輝きを放ち始める。そんな前向きな解釈をしてはいけないだろうか。 書名 星の王子さま 著者名 アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ 新訳 池澤 夏樹 出版社 集英社文庫 |
|
情報通信工学科2年 高橋 万奈 七歳の知能しかもっていない知的障害者に子供を育てることはできるか?私は、この本を読むまでは、父親でも母親でも七歳の知能だったら子どもを愛せないのではないか、親としての意識が薄くてちゃんと責任がとれないから、子どもを育てるとなれば難しいだろうと思っていました。 この本を読み終った時、改めて親子の絆の深さを思い知らされました。知能とかでなくもっともっと重要な愛情のすごさや大切さを確認する事ができました。七歳の知能しかもたない父親サム、父親の知的年齢を追い越した娘ルーシー。この親子の間には、確かに深い絆がありました。 ルーシーは自分の父親の知的年齢を追い越して、父親が少し違うという事に気づき始めました。それでもルーシーは、 「パパが好き。パパの子でよかった。だって、ほかのパパは公園で遊んでくれないもん。」 と、言いました。私はここを読んだ時、ルーシーの父親を想う気持ちにとても感動しました。 「パパの子どもでよかった。」 なんて子どもから言われる父親が何人いるだろうか?どんなに立派な父親でも、本心でこんなことを言ってもらえるのは数人だと思います。だから私はサムは本当にすごいなと思いました。知能なんかよりも、ただひたすらに愛するという気持ちなんだな、と思いました。 私は、この本の中でとても心に響いたサムの言葉があります。サムが裁判官に、ルーシーが十三歳になっても育てられるかと聞かれた時のサムの返事です。 「・・・ぼくにはずっと考えてきたことがある・・・いい親になるには、どうすればいいか。それは、いつも変わらないこと。辛抱強く、話しを聞いてやること・・・話がわからなくても、聞いてやるふりをすること。そして愛すること。」 あっ!こんな簡単な事・・・でも本当に一番大切な事。私はこれを読んで、なんとも言えない感情に襲われました。簡単すぎてびっくりしたんだと思います。でもみんなこれができてないんだと思います。忙しいと言って子どもの言葉に耳を傾けない親。話を聞いてもらうのはとても単純だけど、でもとても嬉しい事です。簡単だけど、難しいこと。簡単だけど、なかなかできない事。簡単だけど、一番大切な事。こんな簡単なことだけれど、絆はとても深まると思います。親達にとったら直球で胸に響く言葉なはずです。私も胸にしまって親になった時思い返してみたいです。 この本から私は、たくさんの事を学びました。サムの言葉に、 「ぼくの手本は、ぼくです。」 と、いう言葉があります。親になると迷いとかも出てくると思うけど、子育てに間違いも正解もないと思うので、自分を信じ、自分を手本にしたらそれが多分正解だと思います。これは人生にもあてはまると思うので、私にも目標とかあるけど、最終的に追い越さなくてはならないのは自分で、最終目標も自分だと胸を張りたいです。私の人生の手本は私です。 この本を読み終えて、七歳の知能だけではいろいろな面で限度があるから、手助けは必要だけど、一番大切な心、愛といった面では、他の父親にも劣らないほど立派な父親になれるという事が分かりました。 どんな人でも、ただひたすらに愛する事。純粋に愛する事。お互いに想い合う事。一番大切な事。この本を読んで改めて思い出さされました。この本と出会えてよかったです。 「 I am Sam 」 脚本 クリスティ・ジョンソン ジェシー・ネルソン 竹書房文庫 |
|
専攻科2年 岸上 沙布 あなたは盲導犬についてどの程度知っていますか?そう訊かれたらどう答えるだろう? 盲導犬を実際に見たことのある人はどのくらい居るだろう?現在日本で働いている盲導犬の数は952頭(2006年3月)しかいないから実際に見たことのある人は少ないだろう。日本で盲導犬を欲している人は5千人近く居るというのに盲導犬の実働数が1000頭にも満たない現状をどれくらいの人が知っているだろうか。 盲導犬を初めて見たとき、その凛々しさに私は驚いたのを覚えている。まっすぐ前を見てパートナーを誘導する、仕事を生きがいとするその姿はとても格好が良かった。毎朝見かけた颯爽と歩く盲導犬とそのパートナーの姿がとても印象に残っている。あるときそのパートナーは変わらず、だが盲導犬が変わっているのを見て私はすごく悲しかったのを覚えている。人間の寿命と、犬の寿命は同じではなく、更に「盲導犬」の寿命は犬のそれよりはるかに短いのだと身をもって感じた。命の儚さと切なさをあれほど悲しく感じたことはない。 盲導犬は何度も何度も別れを味わわなければならない。生みの親との別れ、パピーウォーカーとの別れ、パートナーとの別れ。死ぬまでずっとパートナーと一緒に「盲導犬」の仕事はできない。リタイアした後パピーウォーカーの元に戻れる確率はきわめて低い。盲導犬の一生は別れの連続である。しかし、盲導犬は淋しさを滲み出すことなくまっすぐ前を向いてパートナーと歩んでいく。別れは人を強くする、というが犬も同様に別れの度に強くなり、そして新しい出会いの度に胸を高鳴らせるのであろう。だから盲導犬は強くたくましく輝いているように人の目に映るのだと思う。 盲導犬の一生はもどかしく、思い通りにいかないものだと私は毎回盲導犬の話を聞くたびに思う。パートナーとずっと寄り添っていたいのに体が思うように動かなくなってしまったリタイア犬、パートナーを病で失ってしまったクイール、盲導犬として育てられたのにもかかわらず一度も盲導犬として働くことの無い犬。盲導犬を欲する人はたくさん居るのに一気に世の中に盲導犬を育成し輩出することは不可能であること。盲導犬の育成にかかる費用不足、盲導犬を育成するトレーナーの数不足。全てが思うようにいかず、もどかしい。年々少しずつマスメディアの力を経て盲導犬の実働数は増えてきている。もっともっとまだ盲導犬に出会っていないパートナーに盲導犬と出会ってもらうためには私たち一人ひとりの意識と行動が必要だと感じた。小さなことでいいから盲導犬のために、目が不自由な人のために、社会のために、そういった動きが必要だと思った。 毎朝見かけた盲導犬とそのパートナーは今日もまた一緒に歩んでいるだろう。いつか小さな子供が大きな声でかけた「おはようございます」の声に満面の笑顔を浮かべたパートナーの顔が脳裏に浮かぶ。目が見えない人の目の肩代わりをする盲導犬に、そのパートナーに、もっともっと明るい世界を見せてあげたい。そう思った瞬間をこの本は思い出させてくれた。 石黒健吾・盲導犬クイールの一生 文藝春秋 |
|
|
|
今回の読書感想文コンクールには1年生7編、2年生129編、3年生6編、4年生1編、専攻科生2編、合わせて145編の応募があり、昨年度の157編を下回りました。次回はもっと応募数が増えることを期待します。 |