日揮株式会社
代表取締役社長
森本省治氏による特別講演開催
『エンジニアリング・コントラクターと彼等の課題』
平成15年2月7日(金) 本校視聴覚教室
平成15年2月7日(金),午後1時10分から14時50分まで視聴覚教室において,日揮株式会社 代表取締役社長
森本省治氏(昭和42年3月本校機械工学科卒業)による特別講演「エンジニアリング・コントラクターと彼等の課題」
を行いました.
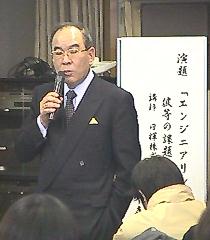 <ご講演概要>
<ご講演概要>
エンジニアリング専業三社といった言葉を新聞紙上で目にされた方は多くても、
社会貢献の割にはその業界の内容は、世間一般には良く理解されていない。
創立75周年を迎える日揮は、どのような会社なのか、過去の変化・困難にどのように対応して成長してきたのか、
不透明で困難な今後の国際競争を、日揮はいかなる戦略を持ってビジネス領域を変化・拡大しようとしているのか、
安定した長期エネルギー資源確保・地球温暖化問題対応が急務なわが国において、日揮が果たせる役割とは何かについて解説する。
また、エンジニアリング・ビジネス業界が求める人材像、及び人材育成に関する基本的な考えについても解説する。
Contents
1. 日揮のあらまし
2. 会社機能の特徴
3. サバイバルレース
4. ビジネス環境の急激な変化
5. ビジネス領域変化/拡大への経営戦略
|
|

|
森本氏から高松工業高等専門学校のみなさんへのメッセージ
「 基礎学力と応用力」
単に暗記に頼った知識ではなく、物事の基本・
本質について充分な理解をともなった学力。
白紙に独自の絵が描ける力。
「気力と体力 」
困難に立ち向かい、それを乗り切る気力・執念と強靭な体力。
「 達成感と感動の経験」
感受性豊かな若いうちに、熱い感動を経験すべき。
「 外国語」
少なくとも英語はMust。ペーパー・テストのための
勉強のみならず、英語によるコミュニケーション能力。
(相手を理解し、相手に対して自分の考えを理解させ納得させ得る力)
|
Q & A
Q1:日揮に就職した動機は?
外国との接点を持つ仕事に就きたかった.山形先生や柴田先生からエンジニアリング会社の事業内容を聞き,興味を持った.
Q2:インターンシップについて
日揮が社員を採用する時に大切にしている一つに,『日揮の仕事が大好きな人・日揮がどうしても採用したいと思う人材,
のみを採用する事』がある.これは採用後にミスマッチが明らかになり,双方が不幸にならないためにも大切な事である.
学生が業務内容をより正しく理解した上で,希望する会社を決める方法として,インターシップは有効であると思う.
|
|

回答する森本氏
|
Q3:英語力について
日揮の社員に対して,『仕事をするための必要な道具として,英語でコミュニケート出来ない者,
PCが使えない者はビジネスの第一線に出れない』と言っている.TOEICで言えば650点のレベルである.
このレベルに満たない者は,昇格などの審査対象外である.同時に,TOEICの高得点者が英語で上手にコミュニケートできる
とは限らない,という事実も承知している.
我々技術者に求められる英語力は,必ずしも高等で難しい英語ではなく,
『英語でコミュニケートする力,相手を理解し自分の意志を正確に伝え,相手を納得させられること』である.
すなわち,語学とか学問と呼ぶほどのものではなく,『慣れ』の部類のものである.したがって,気取る事なく,
もっと気軽に英語で会話をする機会を増やしたら良いと思う.
|
Q4:終身雇用・年功序列と能力主義について
企業は自社に収益をもたらす人材を雇用したいと思っている.
大量生産時代には,一つの仕事に熟練して生産効率を高める雇用形態が企業の利益に結びつき,終身雇用がそれであった.
現在は,顧客のニーズに応じて「価値の創造ができる人材」が求められており,社会の変化にともない雇用形態も変わりつつある.
Q5:学生時代と社会人の違いについて
学生時代は失敗をしても許して貰える場合も多いが,社会においては,会社が法を破れば,抹消され市場から退場を迫られる.
社会人になる時,本気で気持を切り換え,責任を大いに自覚すべきである.
|
質疑応答の後,拍手を持ってご講演に対する感謝の意を表し,
90分にわたる特別講演を終わりました.
森本省治氏のご経歴
昭和42年3月 高松工業高等専門学校機械工学科卒業
昭和42年4月 日本揮発油(現 日揮)株式会社入社
昭和59年9月 国際事業本部SHALCOプロジェクトチーム・プロジェクトマネージャー
平成元年8月 国際事業本部SMDSプロジェクトチーム・プロジェクトマネージャー
平成5年10月 国際事業本部STARプロジェクトチーム・プロジェクトディレクター
平成8年8月 第1事業本部プロジェクトマネジメント第1部長
平成9年6月 理事 第1事業本部副本部長 兼 プロジェクトマネジメント第1部長
平成10年6月 取締役 第1事業本部長代理
平成10年9月 現職のまま、ハーバード・ビジネススクール 研修員(AMP)
平成11年4月 取締役 第1事業本部長
平成12年6月 常務取締役 第1事業本部長
平成13年6月 専務取締役 第1事業本部長
平成14年6月 代表取締役社長(現職)
公職団体経歴及び従事年月
(社)日本産業機械工業会 常任理事 2002年 6 月から現在に至る
特別講演会の様子
このページの内容(本文・写真)は制御情報工学科の提供によるものです
|